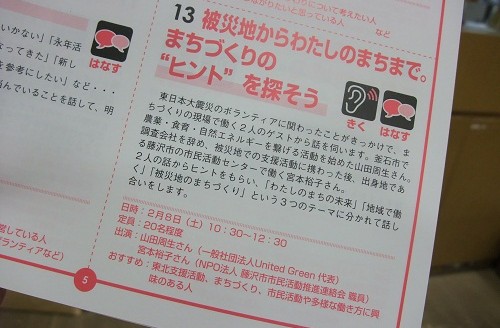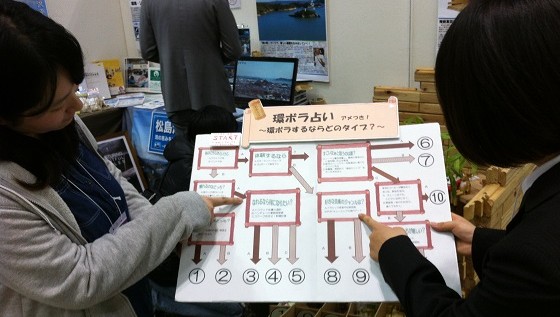クリスマスに寄付について考えてみる。
こんな寄付広告を見かけた方も多いのでは?
NGO/NPOの寄付ランキングを見ると、10位内には子ども支援や緊急人道支援団体が多くランクインしています。目の前の命を助けるという分かりやすいメッセージに対して人々は共感しやすく、また助けたい、放ってはおけないと思う人が多いことの表れでしょう。
日本人には元来、そういう優しさを持っているので、苦しむ人、困っている人を見れば手を差し伸べるし、そういう活動をしている人々に共感しさえすれば、財布の紐も緩む。寄付文化がないと言われる日本ですが、東日本大震災でそれが顕著に見られたように、いざという時には助け合うという共助の気持ちは欧米に負けず劣らず日本人は深いんですよね。
では、環境分野はどうでしょうか?上記のランキングにはほとんど姿が見えません。震災後、助成金や寄付金は環境系から流れた・・・ということもありました。
環境保全をすることは人の命を守る、人の暮らしを支えることに直結していないのでしょうか?
・・・なわけないですよね。
私たちは自然の恵み、すなわち、生きるための水や食糧、気候調整、雨露を凌ぐために家を作る木材など、いわゆる生態系サービスなしには生きていけません。自然を守るのは自然のためではなく、紛いもなく人間が生きていくためのはずです。途上国では、明日の食料のために森林を伐採したり、非持続的な方法で農作物の栽培をするなど深刻な環境破壊があります。災害に対しても脆弱なため、温暖化の影響を受けやすく、環境を守ることが人間の命や生活を守ることに直結しているのが分かりやすいのですが、日本は、食糧や木材、エネルギーなどの資源は輸入に頼り、高度な防災インフラのおかげで、環境破壊や温暖化による影響が見えにくく、なかなか環境を守ることが自分の命や暮らしに直結するということをイメージしにくいのかもしれません。
 そういう意味で、GEOCでお付き合いさせていただいている環境系の団体さんの活動はどれもどれも重要です。
そういう意味で、GEOCでお付き合いさせていただいている環境系の団体さんの活動はどれもどれも重要です。
・・・が、果たして自然を守ることの切実さ、重要さを十分人々に伝えきれているでしょうか。
環境のための環境保全になっていないでしょうか。
NGO/NPOには無縁のことと思いますが、温暖化対策といって数値や機械の性能を追い求めることに走っていないでしょうか。
人道支援や緊急支援の団体のコピーを見て、環境系の団体は、時に“人間”の姿が見えにくいPRになっていることに気づくことがあります。
クリスマス、そして歳末助け合い運動のこの時期に寄付したいと思う人も多いことでしょう。
みなさんはどんな団体を応援したいですか?
。o○★ヾ(´∀`*)Merry☆ Xmas(*´∀`)★。o○
(s.shirai)