- トップ
- GEOCスタッフブログ
- 施設ほか
- マルチステークホルダープロセスは綺麗ごとじゃない!
マルチステークホルダープロセスは綺麗ごとじゃない!
阿賀野川と言えば、新潟水俣病が連想されてしまうような、「公害」のイメージが強い場所です。
この阿賀野川流域で、公害からの地域再生に取り組む「あがのがわ環境学舎」という社団法人があります。
新潟市で開催された、「協働フォーラム」で、お話を聞く機会があったので、どのように、公害問題や地域再生に向けた取り組みを進めているのか、詳しく聞いてきました。
聞けば聞くほど、マルチステークホルダープロセスと呼ばれる、協働の進め方のヒントの宝庫でした。
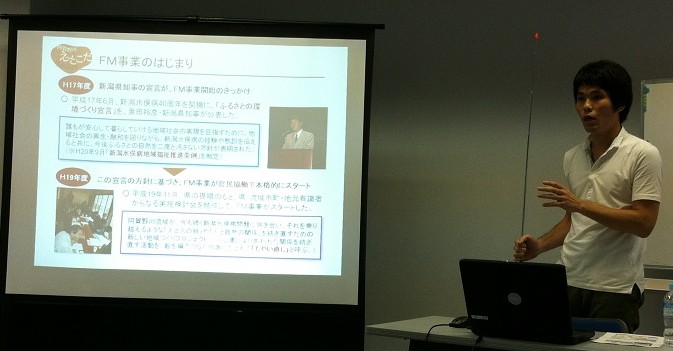
あがのがわ環境学舎の山崎氏
同社は、「ロバダン(炉辺談義)」と呼ばれる寄合を数年にわたり、100回以上開催することで、協働を進めてきました。
この「ロバダン」とは、10名程度の少人数での集まりで、水俣病のことに限らず、フリートークで今感じていることや思っていることを話すものです。
ただ、会の最初に、水俣病について触れるので、自然と水俣病や公害に対する思いが出てくるそうです。
■事前の準備が何より大事!
寄合を持てば、協働の取り組みにつながるかというと、そういうことではなく、事前の準備を怠りません。
必ず、地域のキーパーソンに、じっくり時間をかけて、「ロバダン」を持つための趣旨等を説明します。
その上で、誰を呼ぶのか、いつ開催するのかを調整していきます。
そして、会を運営する時の工夫として、事務局側のメンバー構成とルールに決まりを設けています。
事務局のメンバーには、必ず全ての会に出ている人を2名置くそうです。
そうすることで、情報が散逸せず、集約されます。
情報が集約されることで、コミュニケーションのロスが少なくなり、地域の資源を連結させる際のコーディネートが行いやすくなります。
また、「ロバダン三原則」を設けて、参加された地域の方々に理解を求め、参加しやすい雰囲気を作っています。
ロバダン三原則
- 新潟水俣病のもやい直しが目的とはっきりと伝える。
- 相手の言い分にはまずは耳を傾ける。否定しない。
- 共通の価値観を探る。共通の価値観を広げる。
■小さなことからコツコツと
こうした「ロバダン」を流域一帯で重ねながら、公害問題に向き合う、また地域再生といった動きに繋げていかなければなりません。
ここでも、事務局で主導権を握るのではなく、各ロバダンから、個別のプロジェクトが動き出すのを待ちます。
ロバダンを繰り返すことで、人には話したことのない思いなどが溢れ、具体的なプロジェクトに繋がっていくそうです。
事務局側では、この個別のプロジェクトを応援しつつ、どこの誰と繋げることで、より活動が加速するかを考えます。
そうすることで、流域全体が徐々につながっていきます。
いまは、上流域、中流域で、いくつものプロジェクトが動き、具体的な形になってきています。
今後は、下流域(新潟市方面)にも力を入れていくそうです。
■綺麗ごとではないマルチステークホルダープロセス
ただし、ここまでたどり着くのも失敗の連続だったそうです。
その試行錯誤の結論として、いまの「ロバダン」の形があります。
だからこそ、マルチステークホルダープロセスという言葉には、「綺麗すぎる」という印象を持つそうです。
この「ロバダン」の話を聞くだけでも、準備に非常に時間がかかることもわかるでしょう。
また、終わった後、どのように次につなげていくのかも、とても手間暇かかります。
まったく綺麗ごとではなく、泥まみれになりながらの取組です。
それでも、ここまでしなければ、地域の人と向き合っていくことはできません。
■「負」と「光」を併せ持つ
公害と言えば、「負」の面だけを思い浮かべがちですが、一方で、その地域には必ず「光」の面があります。
「ロバダン」を通して、公害という「負」の面だけではなく、様々な「光」の面が見えてきたことは、この取り組みが、地域を変えつつある、一つの成果だと思います。
この「ロバダン」を通して、「光」の面にも目を向けた、阿賀野川流域を再生するプロジェクトが進んでいます。
流域全体をエコミュージアムにする構想、また環境学習ツアーを事業化していく動きです。
そうした情報を発信するために、「あがのがわ流域再生プロジェクト」のウェブサイトがあります。
ぜひ、のぞいてみて下さい。これから注目の取り組みです。
Takayuki Ishimoto
