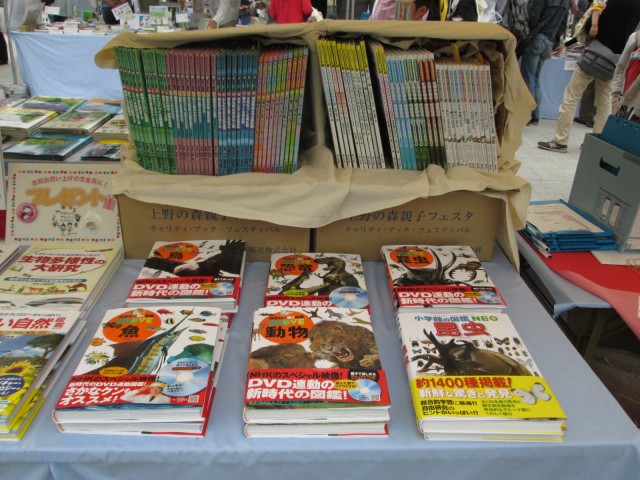組織を活性化させるファシリ術
みなさは、どんな会議をしていますか?
最近、GEOCでは会議スタイルを若干、変更しようと動いています。
・・・ということで、色々模索していたとこともあり、”実行力が高まる会議ファシリテーション4つのルール”なるセミナーに行ってきました。
会議のファシリって、要は会議・議論の進行をスムーズにさせること、でしょ?と思う方、
ブー。(  ̄っ ̄)
確かに、狭義の意味ではそうかもしれませんが、スカイプでもメールでも情報共有できる今、敢えて一堂に会する会議だからこそ、それだけでは十分ではありません。
講師の先生曰く、
創造的な問題解決ができる。
会議後の実行力・アクションに結びつく。
スタッフの成長、組織力の向上を目指す。
ものなのだそうです。
つまり、ファシリ次第で、組織を活性化させることまでできるんですね。
会議の進行役(ファシリテーター)が意識する鉄則ルールは、
●全てのメンバーを意志あるキャストに。
一人一人が必要なメンバーであり、スタッフが自分はチームに必要な存在だと自覚させる工夫や配慮をすることが必要。
リーダーはもちろんですが、記録役であっても、ファシリをする自身も、全員が意見の発信者であろうとする姿勢が大事なので、しゃべりすぎている人がいないか、聞いていない立場の意見はないか・・・。そんなことも気づく必要がありそうです。
●会議のゴール(今日はコレを決める!)を共有する。
出席メンバーや持ち時間などを勘案して、その日、その時間に現実的な着地点を全体で共有する。ただ、○○について話します・・・という漠然とした設定ではなく、○○の問題を共有した上で、その原因を見つけます、解決策を探します、やるかやらないかを決めますなど、具体的な答えが出るように設定するワケです。
先生曰く、会議には、次の3つのタイプがあるのですが、
1)報告/共有の会議・・・ 個人・チームの事象・予定などを報告する場
2)創造的な会議・・・自由な発想を促し、ブレストを行う場
3)収束の会議・・・具体的な問題に対して、問題解決を探る場
日本は、1)や2)のように共有したり、具体的な問題に対して対処する検討会議は得意ですが、なかなか2)創造的な会議の機会は少ないとのこと。おっしゃる通り・・・。おしゃべりから生まれた発明もあるみたいですが、日本人はマジメなので、自由に話し合う=チャットする=無駄話をしている・・・と連想してしまうのか、クリエイティブな発想はためらいがち?
費用も時間も削られる昨今、それらを補うように、朝活やら飲ミュニケーションなど、個人的に、時間外に取り組んでいる人は多いですよね。
会議あるある・・・
●実行するのに議論したはずが、会議、議論したことで満足して、終わってしまう!
経験的に、大きな会議や形式的な会議になればなるほど、その傾向があるかと。
終わった後、で、あれは誰がやるんだっけ?さっきの話何だったけ・・。(・ω・?)みたいな。
なので、必ず、会議の最後には、実行に向けたタスクを洗い出して、役割分担や期限、進捗管理の方法を決めて、行動に移すコミットを確約することを忘れずに。
チームKは実践してまーす。
が、実は苦~い経験があります。(,,-_-)トホホ 会議で話してコミットまではしたんです。・・・が、お互いが理解したことの解釈が違っていたのです。それに気づかず、重大事故になってしまったことがあります。なので、コミットすることに加えて、会議後は、書面(内容の大小によってメモ~覚書など色々)でシェアして、証人(会議参加者)のもと、なる早で確認することを忘れずに。(v^ー゚)
●意見の対立が出た・・・
内心ドッキリしてしまいますが、ここぞ、ファシリ術の見せどころ。
まずは、少なからずの一致点やそもそもの対立点(原因)はどこか(目的、目標、視点、時間軸、役職、立場などから分析)を明らかにしてみる。それらを共有した上で目的に立ち返り、改めて利害が相反しないよう(誰かの負担が大きい、誰かだけが得をするなど)配慮しながら全員が納得いく解を探していく・・・。
言うは易しですね・・・。気配りしながら、会議を進めて自分の意見も出すって、ファシリテーターって、右手と左手でピアノの違う鍵盤を弾くとか、スポーツで言うなら、レフェリーのような・・・? なかなか手腕が問われる難しい役どころですが、実践あるのみですね。
s.shirai