地域に生きる労働運動をNPOと共につくる
~ネットワークSAITAMA21運動~
2004年、(社)埼玉県労働者福祉協議会(以下、埼玉労福協)と連合埼玉を母体とする「ネットワークSAITAMA21運動(以下、ネット21運動)」がスタートした。労働者や退職者が居住する地域で、高齢者・障害者支援、子育て支援、環境保全、まちづくりなどさまざまな活動に参加し、生き甲斐をもって安心して暮らすことのできる地域社会づくりの支援を目的としている。地域のNPOとの連携・協力を模索し、つなぎ役として中間支援組織である「さいたまNPOセンター」との協働で取組を進めている。
右肩上がりの経済崩壊に対応する労働運動の再構築
「右肩上がりの経済が崩れた今、労使交渉による賃上げ、労働政策への提言を主とする従来型の運動だけでは労働者の暮らしを守ることはできない。原点に戻って、労働運動の新しい動きを作る必要があった」。労福協専務理事の鈴木雄一氏はそのように語る。
戦後、日本経済は急速な拡大を続けてきた。終身雇用や年功序列型賃金体系が維持される中、労働者は職場を確保し、より多くの給与を受けることで老後の安心も手にすることができた。働いて経済成長に貢献することが労働者の役割であり、福祉や医療、環境など生活の基盤となるサービスは政府や企業にまかせておけたのである。ところが、この十数年でその前提が崩壊した。いかにして勤労者の福祉を確保できるか、という問いをつきつけられた労働運動は新しい局面を迎えた。
地域に根ざし、地域社会へ参画
鈴木氏は連合埼玉の事務局長をしていた頃から、社会経済情勢の激変に対応した労働運動の再生を考え続けていた。
ネット21運動が目指す基本的な考え方は、地域に根ざし、地域社会と連携した運動である。高齢者・障害者福祉、環境問題、子育てなど暮らしに直結した課題は地域の中で生活する者同士が助け合う「共生」の地域社会によって解決できる。しかし「滅私奉公」で人生の長い時間を過ごしてきた「企業戦士」にとって、職場と家庭の両立すら困難なことも珍しくない。まして地域社会の中での生活領域を拡大することはさらに難しい。個人的な努力で変えるには限界があり、組織的な取組や新たな制度・仕組みが求められる。労働組合が新たな運動の領域として地域を選び、地域で暮らす市民としての勤労者、生活者としての勤労者の支援を使命として生み出した新たな運動が「ネット21運動」である。
中間支援組織を介したNPOとの連携
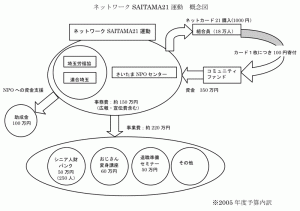 労働組合の組合員が地域で活動を始め、事業を展開する上で、NPOが重要なパートナーとなる、と鈴木氏は考えた。NPOの多くは地域に根ざし、地域の課題解決に対して行政でも企業でもできない方法で、自発的に取り組んでいる。そのような組織との連携を図ることで、労働運動の新しい形を生みだし、埼玉県全体に広げようとしたのである。
労働組合の組合員が地域で活動を始め、事業を展開する上で、NPOが重要なパートナーとなる、と鈴木氏は考えた。NPOの多くは地域に根ざし、地域の課題解決に対して行政でも企業でもできない方法で、自発的に取り組んでいる。そのような組織との連携を図ることで、労働運動の新しい形を生みだし、埼玉県全体に広げようとしたのである。
一方、草の根のNPOの多くは活動範囲が限定され、市町村の中にとどまることから、適切なパートナーを探し、マッチングのプログラムを作るためにはコーディネーターが重要である。ネット21運動設立にあたって、中間支援型NPOであるさいたまNPOセンターに運営委員として参画を求め、さいたまNPOセンターはその要請に応えた。ここに労働組合とその関連組織である労福協とNPOという全国でも珍しい形態のパートナーシップが生まれたのである。
労働者組織と中間支援組織型NPOの連携は、いきなり始まったわけではない。2000年4月、介護保険制度が施行されたとき、さいたまNPOセンターは埼玉県からの委託事業として「介護保険なんでも相談」を実施した。委託事業は1年間で終わったが、依然としてニーズが多かったため、さいたまNPOセンターは独自に事業の継続を決定。そのとき、必要な資金のうち400万円を提供したのが連合埼玉、労福協、全労済であった。この事業がきっかけとなり、ネット21運動での連携につながった。
労働者を地域とつなぐ事業
ネット21運動の事業は次のようなものがある。
- 地域活動への準備として「シニア人財バンク」、「地域デビュー講座」など
- 活動の環境づくりとして「ボランティア養成講座」、「ボランティア情報提供」など
- 地域活動の知識や技能を身につける「NPO設立サポート講座」、「地域環境アドバイザー養成講座」など
- 退職後の生活を支援する「退職準備セミナー」、「年金セミナー」、「賢い消費者セミナー」など
そのうち、地域のNPOとの連携が重要なのは(1)~(3)である。さいたまNPOセンターの理事としてこの事業に関わる東一邦氏は「企業人はほとんどと言って良いぐらいに、NPOやボランティア活動と無縁であり、知識も無い」と断言する。労働組合の組合員がNPOと出会い、活動に参加する機会をできるだけ多く作ることを少しずつ積み重ねて行くしかないのだ。
資金源「ネット21カード」
ネット21運動は事務を労福協に委託している。2005年度は事務経費、事業費を含めて年間約500万円の予算を計上している。ネット21運動はその資金の大部分を「ネット21カード」を使った寄付でまかなおうと考えている。
ネット21カード保持者は1年間、埼玉県や東京都内の飲食店や美容院、ホテルなどが割引料金で利用できる。1枚1000円で販売し、そのうち100円が「ふれあいコミュニティファンド」に寄付され、ネット21運動の資金として使われる。18万人の組合員を擁する組織ならではのスケールメリットを生かした資金調達方法である。
鈴木氏は「寄付文化の創造につながると同時に、組合員のメリットにもなる。1枚1000円だが、家族で1万円の外食をして10%割引なら元がとれる」と言う。「得してボランティア」のキャッチフレーズで今年度3万枚の販売を見込み、資金調達が予定どおり順調に伸びれば、NPOへの資金支援として助成金も予定している。
異文化の壁を乗り越えて
「NPOも労働団体も共に使命を持った非営利組織。連携することで互いにメリットがある」と、東氏は言う。だが、ネット21運動のような、労働組合とNPOの本格的なパートナーシップ事例はほとんどなかった。「企業はトップダウンの縦社会でその上に男社会。そして利益につながらないことには 関心が無い。それに対して、NPOは水平の人間関係だし、女性が多い。もうからないことに一所懸命になる。全く違っているから、接点が少なかったし、嫌っている人すらいる。いきなり共同で何かをしようとしても、互いに組織文化が違うし、極端に言えば、言葉が通じないこともある」。いわば水と油のような両者の間に立って、つなぎ役となる中間支援組織の役割が重要なのだ。
関心が無い。それに対して、NPOは水平の人間関係だし、女性が多い。もうからないことに一所懸命になる。全く違っているから、接点が少なかったし、嫌っている人すらいる。いきなり共同で何かをしようとしても、互いに組織文化が違うし、極端に言えば、言葉が通じないこともある」。いわば水と油のような両者の間に立って、つなぎ役となる中間支援組織の役割が重要なのだ。
東氏は「2007年以降、団塊の世代と呼ばれる人たちが定年を迎え、地域に戻って来る。企業人が、NPOやボランティア活動にソフトランディングできるかどうか、NPOにとって大きな課題だ。私たちはこれをNPOの2007年問題と呼んでいる」と言う。多様な知識や技術を身に付けた元気な退職者が地域で活動をする機会が今よりもずっと増えるに違いない。それは歓迎すべきことである一方、企業とNPOの文化の違いが摩擦となり、ようや根付き始めた市民社会への足取りに悪影響が出ることをおそれている。ネット21運動への参画は、NPOにとっても重大な危機感を背景としているという。さらに東氏は、NPO側にも問題があるという。「企業のボランティア活動に期待する役割が、自動車の運転や力仕事しか思いつかないということもある。受け入れるNPOも企業との接点を増やすことによって、もっと良い関係を築くことができる」と強調していた。
埼玉県のように東京都に通勤する人が多い地域で顕著に表れる可能性があるが、同様な問題は多かれ少なかれ全国で起こると考えられる。そうした問題解決に向けての、労働者組織とNPOとの共同を進める先駆的事例となるのではないだろうか。
参考URL
(社)埼玉労働福祉協議会 ネットワークSAITAMA21運動
