住民・NPO・行政の協働でつくる
「ツルと人・共生の里」再生構想
NPO法人ナベヅル環境保護協会、周南市、山口県ほか
あらまし
本州で唯一、ツルが飛来する山口県周南市(しゅうなんし)八代(やしろ)地区。人々は江戸時代よりツルと共に暮 らし、大切に守ってきた。かつてツルは西日本一帯にやってきたが、開発による環境の変化などにより、ナベヅルが飛来するのは鹿児島県の出水市(約7,000羽)と周南市八代地区(13羽)だけになってしまった。ツルと共生してきた八代地区でも飛来数は年々減少し「このままではツルがいなくなくなってしまう」という状況となったことから、地元住民や行政はツルを保護するための活動を行っていた。
らし、大切に守ってきた。かつてツルは西日本一帯にやってきたが、開発による環境の変化などにより、ナベヅルが飛来するのは鹿児島県の出水市(約7,000羽)と周南市八代地区(13羽)だけになってしまった。ツルと共生してきた八代地区でも飛来数は年々減少し「このままではツルがいなくなくなってしまう」という状況となったことから、地元住民や行政はツルを保護するための活動を行っていた。
平成15(2003)年、八代地区はそれまでの熊毛町八代から、合併により周南市八代となった。熊毛町はシンボルであるツルと共生するまちづくりをうたっていたが、合併後に出来たまちづくりプランから、ツルとの共生の視点が抜けてしまった。「何とかしなければ」と感じた地元住民やNPOが、地元発のまちづくりプランを作ることになり、その際に行政職員らはアドバイザーグループを立ち上げ、行政にも受け入れられやすいプランとなるよう、サポートした。こうして出来た“「ツルと人・共生の里」再生構想”は、周南市長、周南市議会議長、山口県知事に提出され、地元発のプランが、実現に向けて動き出している。
地域のシンボル、ナベヅルが少なくなった
八代地区の人々は、江戸時代からツルを保護し、ツルと共生しながら暮らしてきた。江戸時代、幕府はツルの捕獲を禁じていたが、明治維新により禁止令も自然消滅し、各地でツルが乱獲されるようになった。 ところが八代村(当時)は古くからの習慣を守り、村人の申し合わせでツルを守ってきた。
明治20年頃には、かつて西日本全域にあったツルの越冬地も、鹿児島の出水や、ここ八代などごく限られた地域となった。こんなエピソードが八代に伝わっている。“各地でツルが減ってきたので、他所から八代村に猟師がやってきて、ツルを撃ってしまった。怒った村人は、猟師を取り囲み大騒ぎとなった。”― これが契機となり、明治20年に山口県知事は“八代村のツルの捕獲を禁じる県令”を発した。これは、近代日本で初めての自然保護法令にあたる。
このように地域は懸命にツルを保護してきたのだが、戦後、田の圃場整備や近隣でのゴルフ場開発、新幹線や高速道路の開通など、ツルの生息環境が少しずつ変化していった結果、八代に来るツルの数は年々減っていってしまった。
世界各地には15種のツルがおり、日本で主に見られるツルは、ナベヅル、マナヅル、タンチョウの3種。タンチョウは北海道にのみ生息する留鳥で、ナベヅル、マナヅルは夏にロシアや中国で繁殖し、日本で越冬する渡り鳥だ。八代地区にやってくるのはナベヅルで、全長約100cm、翼長約180cmとなる。毎年10月下旬から朝鮮半島経由で飛来し、3月上旬まで日本で越冬する。国内最大の越冬地は鹿児島県出水市で、毎年7000羽ものナベヅルが飛来する。環境省レッドリスト絶滅危惧II類。
ナベヅルは家族単位で暮らし、一度つがいになると、どちらかが死ぬまでパートナーを変えないといわれる。夏にロシアで産まれた雛を連れやってきて、いつも家族単位で行動する。八代地区の場合、夜明け頃に山中の田などのネグラから盆地の田へ餌を探しにきて、日中の大半は右の写真のように落穂を食べる。警戒心が強く、家族の誰かが見張りをしながら、他の家族と距離を保ち(縄張り)過ごす。日が暮れる頃、ネグラに帰っていく。
現在、ナベヅルの越冬地は出水市に集中しており、一箇所に集中することは鳥インフルエンザの流行などの危険性がある。山口県では鹿児島県と協力し、傷病により保護した出水市のツルを、周南市に移送してリハビリ後に放鳥をする計画があり、今年にも実施される予定。
八代からツルが消えてしまう・・・そして市町村合併
平成元(1989)年に65羽飛来したが、48羽、41羽、39羽、31羽・・・と年を追う毎に飛来数は減っていた。平成6(1994)年(飛来数27羽)には、文化庁から山口県に対し、天然記念物であるナベヅルの保護を強化するよう指示があった。
その一方で地元も危機感を募らせ、“八代のツルを愛する会”は、1995年に全国のツル研究者を招き「ナベヅルサミッ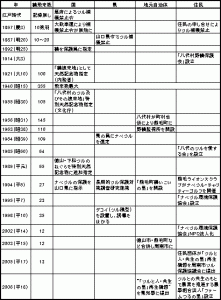 ト」を開催した。そ
ト」を開催した。そ の席上、長年に渡り八代のナベヅルを観察してきた研究者から、「このままいくと、2~6年後にツルが来なくなっても不思議ではない。」という衝撃的な調査結果が報告された。特に問題なのは、親鳥と暮らしていた幼鳥が独り立ちした後、パートナーを見つけるまで若鳥グループに入るが、そのグループが八代にほとんど来なくなったことだ。新たな世代が来なければ、確実に八代からツルがいなくなってしまう。給餌などの保護活動だけでなく、それまでの保護活動グループ、地元、町内各団体の代表者が集まり、ネグラ、餌場の整備に関する行政への要望、普及啓発、募金活動で連携するために“ナベヅル環境保護協会”(2002年にNPO法人化)が発足した。
の席上、長年に渡り八代のナベヅルを観察してきた研究者から、「このままいくと、2~6年後にツルが来なくなっても不思議ではない。」という衝撃的な調査結果が報告された。特に問題なのは、親鳥と暮らしていた幼鳥が独り立ちした後、パートナーを見つけるまで若鳥グループに入るが、そのグループが八代にほとんど来なくなったことだ。新たな世代が来なければ、確実に八代からツルがいなくなってしまう。給餌などの保護活動だけでなく、それまでの保護活動グループ、地元、町内各団体の代表者が集まり、ネグラ、餌場の整備に関する行政への要望、普及啓発、募金活動で連携するために“ナベヅル環境保護協会”(2002年にNPO法人化)が発足した。
これと平行して周南市は補助を受け、ツルのねぐらである山中の土地購入、冬場の田に水を張り(冬季湛水)をし、餌となるドジョウを放すなど事業を行い、山口県でも新たなツルを呼ぶためにデコイ(模型)を設置しツルを呼び寄せる手法などで、県教育委員会が文化財保護施策を行った。地元唯一となる八代小学校でも、子どもたちがツルの観察などを行い「ツル日記」を作成するなど、ツルを題材にした環境教育が行われている。
平成15(2003)年4月21日。全国で市町村合併が進む中、八代地区がある熊毛町は、周辺の徳山市・新南陽市・鹿野町と合併し周南市となった。熊毛町では、町のシンボルであるツルと共生するまちづくりが重視されていたが、合併後の周南市という大きな枠組みになると、ツルとの共生は薄れてしまい、地元は困惑してしまった。ツルを保護には、ツルの暮らしやすい環境を地域全体で整備していく必要があり、そのための“まちづくり”が欠かせないからだ。
住民が作る“「ツルと人・共生の里」再生構想”
周南市庁が置かれた旧徳山市は、コンビナートを擁する人口10万を越す工業都市であり、人口約16,000人の熊毛町が取り組んできたツルと共生するまちづくりを全市的に行うことはなかった。「ツルが来なくなりそうなのに、このままではツルと共生するまちづくりが出来ない」そう感じた住民は、これまで熊毛町で行ってきた取り組みを周南市になっても継続することを検討した結果、まちづくりプランを自らの手でつくり、市や県にアピールしていく事とした。プラン作成にあたり、山口県庁や周南市役所の担当者に相談したところ、地域の熱意を感じた県や市役所の職員がアドバイザーグループを立ち上げ、ボランティアとしてプラン作りに協力してくれることになった。行政のプロであれば「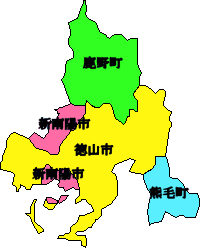 どのようなプランであれば行政も応援できるか」は、知り尽くしている。
どのようなプランであれば行政も応援できるか」は、知り尽くしている。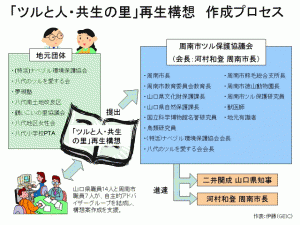
こうして、住民・NPOが主体として作った構想案が平成17(2005)年10月、周南市長、周南市議会議長、周南市ツル保護協議会会長(天然記念物保護のための法に基づく組織、会長:河村和登 周南市長)の三者に提出された。そして協議会で協議・承認され、同協議会会長名で山口県知事と周南市長(市長は協議会会長でもあるので、自分自身に送る形となる)に対し、進達という形で提出された。これにより、今後の周南市や山口県の政策に、これまで以上にツルと共生する地域づくりが行われる目処がついた。“市民が主体となって計画づくりをし、それを行政職員がボランタリーにサポートする”という形だが、全国的にもこうした事例は珍しいのではないだろうか。
■参考資料:
「ツルと人・共生の里」再生構想(PDFファイル:422KB)
提供:特定非営利活動法人 ナベヅル環境保護協会
取材を終えて
現地を訪れてまず感じたのは「何故ここが本州唯一のツル飛来地なのか?」という事だった。八代地区は周囲を低い山に囲まれた標高320m、1.5平方キロのほどの小さな盆地だ。車で1時間ほどの距離にある山口県庁へ行く際も、似た景色の場所が沢山あり不思議だった。本来ナベヅルは、鹿児島の出水のような、外敵をすぐに見つけられる広い平地の田を好むが、八代地区はそうでもない。必ずしもツルにとって都合の良い訳ではない地にやってくるのは、彼らにとっての伝統なのだろうか。八代地区は、数百年もの長きに渡りツルと共生する文化を作り上げてきた。そしてツルの間でも「八代に行けば人は襲っては来ないし、快適に暮らせる」という事を、親から子へと代々伝えているのだろう。ナベツルという野生動物が、人と共生する術を知っていて、本当の意味で人と動物が共存している事に感動した。
しかし、一言で「自然との共存」という美しい言葉だけでは片づけられない苦労が、現地にはあった。ツルがやって来る10月下旬から3月上旬にかけ、地元では野外の作業を行わない。冬場の裏作で麦を作る事もできるし、中山間地域の冬場の重要な収入源の一つである圃場整備や道路整備などの公共事業も、ツルがいる間は行わない。そうした犠牲を払ってでも、地元の人々は伝統的にツルと共存する暮らしを続けてきた。地元の人もそうした事はあまり口に出さないが、影でそうした苦労をされている。
今回お話を伺った方のお一人、ナベヅル環境保護協会の西岡武美会長は、地元で生まれツルと共に暮らしてきた。地元で会社を営んできた西岡さんは、地元ライオンズクラブなどの活動を通じ、鹿児島県出水市のライオンズクラブと交流を持ったり、熊毛町時代から行政と様々な交渉を行うなど、精力的に活動されている。「凄いですね」と言うと「ツルのお陰です、ツルによって私たちは生かされています」とおっしゃった。同協会の事務局長の末松幹生さんも、やはり同じ事を言われた。
周南市役所の立場からお話を伺ったのは、教育委員会生涯学習課鶴担当の徳永豊さんだ。徳永さんは個人的に環境教育に長年取り組んで来た方で、(社)日本環境教育フォーラムの理事でもあり、麦を栽培しパン作りまで行う食育の活動もされている。「個人で環境教育をやってきたが、ようやく役所の仕事とリンクできた」といわれていた。
私はツルを初めて目にしたが、翼長180cmもの大きな美しい鳥が舞う様は、素直に感動する。私のような短期の取材者には計り知れないご苦労を地元の方はされているのだとお察しするが、地域のシンボルとして人々に愛されるツルと、人が共に暮らしていく文化が受け継がれ、誇りの持てる地域であり続けて欲しいと感じた。
- 取材先
- 関連リンク
- 鶴いこいの里(周南市)
- 参考図書
- 八代のナベヅル
1998年3月 編:ナベヅル環境保護協会
発行:中国新聞社 ISBN4-88517-262-4 C0040
- 八代のナベヅル
- 参考リンク
- 渡り鳥生息地ネットワーク これまでの渡り性水鳥の保護・調査活動 ナベヅル調査(環境省インターネット自然研究所)
- 農業農村整備事業と多面的機能-八代地域-(中国四国農政局)
伊藤博隆@地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)
松尾健司@中国環境パートナーシップオフィス(EPOちゅうごく)
