森林NPOと地元との協働による森の再生が
市民団体初のFSC取得を契機にさらに広がる
相模湖町住民とNPO法人緑のダム北相模の取り組み
あらまし
今回の事例は神奈川県北部の山間地で、山主とNPOが協働して、ボランティアベースで山の手入れを行い、世界的にも例を見ない、市民団体によるFSC(森林認証)取得など、活発な活動が地域活性化にも大いに貢献している“緑のダム北相模”の取り組みを紹介する。
ハイキングで訪れた森の異変を実感した
緑のダム北相模の事務局長を務める石村さんは山歩きが好きで、首都圏近郊の山を度々訪れていた。そして、たまたま訪れた相模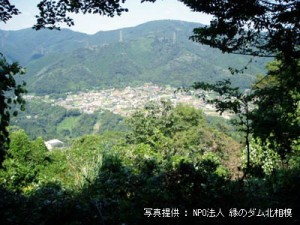 湖周辺の森を歩いていた時、鬱蒼として静寂に包まれた森に出会った。通常であれば、森を歩いていればそこに住む生き物の気配が感じられるものだが、そこはあまりにも静かだった。その後、日本の森林の現状に警鐘を鳴らす新聞記事に目に留まった。輸入木材の増加によって国内の木材相場が値崩れし、その結果、山が放置されて荒れている、という内容の記事だった。「そうか、そういう理由であの山は荒れていたのか」と合点がいった。それから色々と調べ、大学教授、行政、NPOなどあちこちを訪ね歩く中で、NPO法人森づくりフォーラムで代表をされていた園田安男さんと出会った。
湖周辺の森を歩いていた時、鬱蒼として静寂に包まれた森に出会った。通常であれば、森を歩いていればそこに住む生き物の気配が感じられるものだが、そこはあまりにも静かだった。その後、日本の森林の現状に警鐘を鳴らす新聞記事に目に留まった。輸入木材の増加によって国内の木材相場が値崩れし、その結果、山が放置されて荒れている、という内容の記事だった。「そうか、そういう理由であの山は荒れていたのか」と合点がいった。それから色々と調べ、大学教授、行政、NPOなどあちこちを訪ね歩く中で、NPO法人森づくりフォーラムで代表をされていた園田安男さんと出会った。
友人、知人に日本の森の現状について語るうちに、友人の一人が“親戚が相模湖に山を持っている”事が分った。ある日、下見に行ったところ案内をしてくれた地元の方より「木が売れなくなって困るご時勢に、あなたたちは仏さんのようだ」とも言われた。
こうして平成10年から石村さんを中心として仲間を集めて、神奈川県相模湖町(新宿より中央線快速で約1時間)での森に入るようになった。森づくりフォーラムの園田さんも、東京都の日の出町から参加してくださる事になった。
林業や、森作りに関して考えるときには、長い周期で考えなければならない。何故なら、植林してから材として伐採するまでには概ね50~100年掛かるので、複数の世代に跨って計画を立てる必要がある。日本の森は、明治に入って廃藩置県がされた時に、統制が効かなくなって森林の乱伐が起きた。その後は管理された造林が行われたが、戦中~高度成長期にかけて森林資源が大量に消費された。そして現在では、平成16年度の林業白書によると、『我が国の森林は、「伐らないで守る時代」、「植えて回復する時代」を経て、「成長した森林を活かす時代」に入っている。』と記されている。
その一方、WTOやプラザ合意などを経て、市場がグローバル化した今では、国内林業の採算性は厳しい。昭和36年に輸入が自由化されて以来、価格の安い外国産材(外材)の輸入が増え続け、国内の林業は厳しい状況に置かれている。(下図参照)
しかし、日本の森林率は66.4%と先進国の中でもトップクラスであり、森林資源に恵まれた日本が貴重な資源を輸入に頼ることは、国際的な批判の対象となり得る。そんな中でも最近は、木材消費が急増する中国に向けて、日本の杉材が高級建材として輸出が開始されたり、山林の多面的な機能の中でも特に重要な水源かん養のための資金確保のために「水源かん養税」や「水源税」などが各地の自治体で検討されている。林業白書でも、“緑のダム北相模”のようなNPOやボランティアに大いに注目しており、今後は林業としての市場経済の中の枠組みだけでなく、様々な形で森林の維持管理、ひいては国土の保全がなされていく事が期待されている。
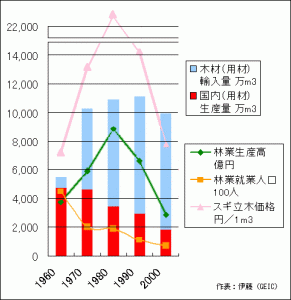
| 和暦 | S35 | S45 | S55 | H02 | H12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | |
| 木材(用材)消費量 | 万m3 | 5,478 | 10,268 | 10,896 | 11,116 | 9,926 |
| 木材(用材)輸入量 | 〃 | 754 | 5,644 | 7,441 | 8,179 | 8,124 |
| 木材自給率 | % | 86.2 | 45.0 | 31.7 | 26.4 | 18.2 |
| 林業生産高 | 億円 | 3,741 | 5,900 | 8,855 | 6,612 | 2,866 |
| 林業就業人口 | 万人 | 45 | 20 | 19 | 11 | 7 |
| スギ立木価格 | 円/1m3 | 7,184 | 13,168 | 22,707 | 14,206 | 7,794 |
誤解を乗り越えて
順調に進めてきたボランティア活動であったが、地元から理解を得る事は難しかった。地元の人にとっては、マナーの悪い都市からの観光客に悩まされ続けてきたからである。ハイキングにやってきて、所有者の断りも無く勝手に森に入り、ゴミを捨てて帰ったり、ひどい者は勝手に焚き火や不法伐採までしていたという。そういう状況であったので、石村さんたちの活動に対しても、「好き勝手やる都会の団体」にしか見えなかったのだろう。
石村さんたちは、地元の理解を得ることが重要と、「急がず、休まず、楽しく、無理せず、ボチボチと・・・、そして、たくさんの参加で森は良くなる。」をモットーに雨の日も寒い日も、休まず地道に活動を続けた。また、“森の中で音楽会”や地元の子どもたちを対象にした“森林体験講座”などを開催し、地元とのコミュニケーションを活発化し、「荒れた森林の再生」を目指す活動である事をアピールした。そうしたひたむきな活動が功を奏して、平成13年には相模湖町の駅から徒歩10分の好立地に60haの広大な森林を持つ鈴木重彦さんと出会う。鈴木さんは旧内郷村の森林組合長も務めた人で、会の活動に協賛して快く所有している森林を開放してくれた。この森は、その地区の名前から「若柳・嵐山の森」と名付けられ、現在も活動の拠点となっている。会の活動は地元にも浸透し、認められるようになっていった。
活動が広がる
石村さんは活動を広げるにあたり、あちらこちらを精力的に見て回った。2001年2月には、日本で初めてFSCを取得した速水林業(2000年 2月取得)を見に行き、世界的に見ても高い水準で管理された森とその経営哲学に感銘した。ここまでの活動は出来ないと思っていたが、やはりFSCを取得した別の場所を見た時に「これなら我々でも出来る」と思い、FSCのガイドラインに沿った森林管理を目指して、2001年5月には「FSC取り組み5ヵ年計画」を立てた。また2002年には、内閣府認証(活動拠点が東京と神奈川に跨るため)のNPO法人格を取得している。
2月取得)を見に行き、世界的に見ても高い水準で管理された森とその経営哲学に感銘した。ここまでの活動は出来ないと思っていたが、やはりFSCを取得した別の場所を見た時に「これなら我々でも出来る」と思い、FSCのガイドラインに沿った森林管理を目指して、2001年5月には「FSC取り組み5ヵ年計画」を立てた。また2002年には、内閣府認証(活動拠点が東京と神奈川に跨るため)のNPO法人格を取得している。
こうした非営利活動に際して常に課題となるのが資金の問題だが、企業や行政の持つ助成金を活用している。しかし、こうした助成金も多くは事業に対する助成であり、人件費などの事務局経費を捻出出来ないものも多いのだが、ごく最近ではこうした人件費や事務所経費にも使える基金が出てきており、緑のダム北相模でも、セブン-イレブン緑の基金が2004年度より開始した、「先駆的、総合的、組織的に活動し、技術や手法を他へ波及できる団体の事務局運営基盤を支援」を目的としたパートナーシップ助成の制度による助成金を受けている。
森林の整備に参加するボランティアも増え、中には不登校の生徒たちを先生が引率して参加するグループもあり、森林セラピー的な機能も有している。また、メンバーが増えるにつれ様々なアイデアを持った人も増えてきており、中には養蜂に挑戦するメンバーもいるなど、それぞれの個性や特技を活かしたプロジェクトも開始されている。
また神奈川県では、水源環境保全・再生に関して県民参加で施策のあり方について検討を重ねてきたが、そうした対話プロセスの中でも“緑のダム北相模”は積極的に提言を行い、結果的に「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」にも反映されている。
FSCの取得、これから
2001年からFSCのガイドラインに沿って活動を続けてきた結果、2005年11月にFSCの認証が得られた。もちろん、簡単に取れたわけではなく、ボランティアを中心に地道に活動を続けてきたことと、地元、行政、研究者、FSCの認証機関であるSGSジャパン株式会社など、多くの関係者の協力があったからこそだ。FSCには、森林管理認証(Forest Management Certification:FM認証)、COC認証(Chain-Of-Custody Certification:加工流通過程の管理の認証)の2種類の認証があり、緑のダム北相模でもそれぞれ取得している。
FSC認証が目的で活動してきた訳ではないのだが、世界的に見ても市民団体でFSC認証を受けた初の事例だということで、グループの意識も変わった。しかし、目的と手段を見誤らずに、今後はさらに発展していきたいと考えている。取り組み目標としては、衰退が激しい神奈川の林業を何とか復活させ、県産材を流通させたいという点だ。現在は、家具メーカーに声をかけ、FSC認証の木材を使った学童用の机や椅子が出来ないかと、検討を重ねている。また石村さんは、これまでの活動の中で、市民の力の大きさを認識しており、多くの人が参加することで環境を保全していくのが良いという思いに至った。そこで、「神奈川発の世界の森林保護運動」をやりたいと、神奈川県やFSC本部にもアプローチしている。森の維持管理を行うボランティアを組織して、多くの人が参加する受け皿が整い、更に国際的な認証を受けたことで、組織として強い基板が出来た。今後は、森からの恵みで広く様々な団体との協働が広がっていくことだろう。相模川の上下流との流域連携や、旧甲州古道による周辺地域の自治体や団体との連携も始まっている。
取材を終えて
森林ボランティアというと、林業のプロからすれば、「道具も違うし技術も経験も違う一般の人に、森林の維持管理は無理だ」という声もある。しかし、日本の山は急な斜面も多く、そうした地形的要因から外国のような大型重機により森林作業に向かない点が、国際競争力の上ではウイークポイントになる部分もあった。確かに、林業のプロから見れば効率が悪い部分も多いのだが、市民による森林管理には大きな可能性があると感じた。人口比で見 れば一握りの専門家だけが森を守るのでなく、圧倒的大多数のごく一般の人が参加し、自ら様々な事を感じ取って発見することこそ、大事だという発想だ。都市に住む人の割合が全人口の80%にも登る日本では、多くの人がガスや電気といったエネルギーを大量に使うライフスタイルを送っている。良く言われる話ではあるが、そうした自然環境と隔絶した生活をしている人こそ、山に入って人間本来の機能を発揮することで、環境を理解するだけでなく精神的な安らぎを得る事が出来るのではないだろうか。緑のダム北相模の活動理念も、「森林破壊という負の遺産を子孫に残してはならない」とし、そのためにFSCガイドラインに沿った、新しい森林再生事業を創出するとううものだ。これは決して大げさなミッションではなく、森林の再生を真剣にバックキャスティングで考えて掲げているものだ。
れば一握りの専門家だけが森を守るのでなく、圧倒的大多数のごく一般の人が参加し、自ら様々な事を感じ取って発見することこそ、大事だという発想だ。都市に住む人の割合が全人口の80%にも登る日本では、多くの人がガスや電気といったエネルギーを大量に使うライフスタイルを送っている。良く言われる話ではあるが、そうした自然環境と隔絶した生活をしている人こそ、山に入って人間本来の機能を発揮することで、環境を理解するだけでなく精神的な安らぎを得る事が出来るのではないだろうか。緑のダム北相模の活動理念も、「森林破壊という負の遺産を子孫に残してはならない」とし、そのためにFSCガイドラインに沿った、新しい森林再生事業を創出するとううものだ。これは決して大げさなミッションではなく、森林の再生を真剣にバックキャスティングで考えて掲げているものだ。
中心になって事業を引っ張っている石村さんは、バイタリティに満ちている。エネルギッシュに活動する、というだけでなく、事業の発展のさせ方が上手な方だと感じたのだが、これまでに幾つもの会社を経営してきたそうだ。緑のダム北相模の運営にも、そうしたノウハウが至るところで発揮されている。「行政と対峙することがあっても、決して怒らない。ケンカしても何も生まれないから。」など、含蓄のあるお話を数多く伺った。事業やパートナーシップの広がりが非常に楽しみであり、今後も注目していきたい。
- 取材先
- 関連リンク
- 参考図書
- 『自然再生に向けた各地取り組みの取材報告集』
2004年3月 発行:環境省自然環境局自然環境計画課 - 森、里、川、海をつなぐ自然再生 全国13事例が語るもの
2005年7月 自然再生を推進する市民団体連絡会
発行:中央法規出版
- 『自然再生に向けた各地取り組みの取材報告集』
- 参考リンク
