ランドスケープに沿ってゆるやかに連携する
「いるか丘陵ネットワーク」
大地のつながりを生きものの姿でとらえる
首都圏中央に、関東山地と太平洋をつなぐ「多摩・三浦丘陵群」と呼ばれる丘陵域がある。高尾山の東に発し、境川と多摩川に挟まれて、東京都町田市から神奈川県横浜市中央部を貫いて南東に延び、逗子・鎌倉から三浦半島にいたる全長70キロ、総面積700平方キロのこの地域は、約700万人が住む人口密集地だ。それにもかかわらず、ここはまだ貴重な自然が散在する「巨大な緑の回廊」である。その広がりを宇宙から見ると、バンドウイルカがジャンプしている姿に見えるため、この丘陵群を愛着を込めて「いるか丘陵」と呼び、小網代、円海山、柏尾川、帷子川、鶴見川流域、多摩川南崖線などで活動する市民団体が、流域ベース・丘陵規模でゆるやかに連携する「いるか丘陵ネットワーク」を形成している。
いるかの頭部から背中を占めるのは鶴見川流域。その源流域は、ちょうど「いるかの瞳」に位置し、最源流部の谷だけを見るとまるで羽を広げた「カワセミ」のようだ。流域面積235平方キロメートルの外形は「バク」の姿に似ている。鶴見川が刻む多摩丘陵は、その南端で三浦半島とつながり、「いるかのしっぽ」である小網代の森までつながっていく。「いるか丘陵ネットワーク」では、広範なランドスケープを、このようにカワセミ、バク、いるかなどと、しばしば生きものの姿にイメージし、大地のつながりを共有しつつ、自然環境重視の地域文化の形成に取り組んでいる。
持ち場なくして連携なし
流域規模の大きな活動が進んでいるのは、鶴見川の流域だ。この流域におけるネットワーク活動は、どのような仕組みで展開されているのだろう。鶴見川は、町田市北部に源流を発し、多摩丘陵、下末吉台地を刻み、横浜市鶴見区生麦で東京湾に注ぐ一級河川だ。本流は全長ほぼ42.5キロ。恩田川、早渕川、矢上川などの支流が合流して鶴見川水系を構成している。流域では、上流から下流まで、川や雑木林で活躍する自然グループ、まちづくりグループ、地域文化活動団体など、現在35団体が連携した活動が展開されている。
「鶴見川流域ネットワーキング(TRネット)」とよばれるこの連携活動は、参加団体の持ち場ごとの日常活動を基盤として推進されている。TRネットは、1980年代後半から流域視野で環境再生をめざす市民の動きが出てきたのを背景に、1991年、任意のネットワーク活動として誕生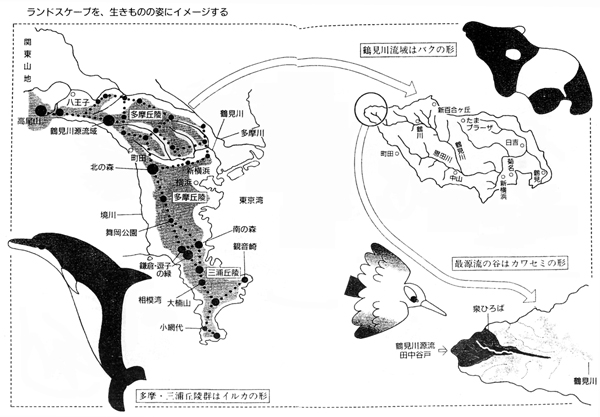 した。以来、鶴見川の水系に沿って自然や都市を学び直し、バクの姿の流域地図を共有しながら流域規模の市民連携を進め、「安全・安らぎ・自然環境・福祉重視の川づくり・まちづくり」を通して、持続可能な未来を開く新しい流域文化を育くむためのさまざまな流域活動を進めてきた。2003年、それまでの活動の成果を受け、新たにNPO法人「鶴見川流域ネットワーキング(npoTRネット)」を設立。任意組織としての従来のネットワークは「連携・鶴見川流域ネットワーキング(連携TRネット)」と改名・改組されて今日に至っている。源流から河口まで流域を8つの亜流域にわけ、対応するサブネット組織を基本として、行政、地域の企業、市民活動相互の連携を進めるのは従来通り。全体の事務局をnpoTRネットが担当している。
した。以来、鶴見川の水系に沿って自然や都市を学び直し、バクの姿の流域地図を共有しながら流域規模の市民連携を進め、「安全・安らぎ・自然環境・福祉重視の川づくり・まちづくり」を通して、持続可能な未来を開く新しい流域文化を育くむためのさまざまな流域活動を進めてきた。2003年、それまでの活動の成果を受け、新たにNPO法人「鶴見川流域ネットワーキング(npoTRネット)」を設立。任意組織としての従来のネットワークは「連携・鶴見川流域ネットワーキング(連携TRネット)」と改名・改組されて今日に至っている。源流から河口まで流域を8つの亜流域にわけ、対応するサブネット組織を基本として、行政、地域の企業、市民活動相互の連携を進めるのは従来通り。全体の事務局をnpoTRネットが担当している。
TRネットの活動の基本方針の1つに「持ち場なしに連携なし」というものがある。この活動スタイルをnpoTRネット代表理事の岸由二氏は「商店連合型」と表現する。「はじめに店ありき、が基本です。活動実体のないところでネットワークをつくろうとしても仕方ありません」
日ごろは各々の団体が持ち場で活動し、イベント時などに人手が足りなければ互いに応援に駆けつけるというスタイルだが、恒例となった「つるみ川新春ウォーク」など合同で行うイベントもある。2日間かけて源流から海に注ぐ河口まで42.5キロを歩き通すもので、歩きながら時折ふり返ると富士山がきれに見える富士見スポットもある絶好のウォーキングルートだ。区間ごとにその地域で活動している団体がガイド役を務め、川沿いの動植物や流域の歴史について解説してくれる。今年は1月7~8日に行われ、水系を管轄する国土交通省などの行政からの参加者を含む、延べ170名の参加があった。
もちろんイベントばかりでなく、ホームページなどを通した河川流域情報の一般広報のほか、国や地元自治体が市民参加の地域づくりを進める際にも、協働事業のパートナーとして積極的に貢献してきた。鶴見川流域水マスタープランや河川整備計画などの検討でも、委員会への参加、情報や事例の提供、懇談会などへの市民参加の促進など多彩な協働を進めてきた。行政との信頼関係も、多くの団体が各自の持ち場で長年にわたって地道な活動を続け、人、情報の膨大な蓄積を持つからこそ築けるものだろう。
ランドスケープが訴える可能性
鶴見川流域ほどの密度ではないが、小網代や円海山などの拠点を含む広義の三浦半島域や、横浜・川崎の多摩丘陵域でも、持ち場ごとの日常活動をゆるやかにつなぐネットワークが形成されており、かながわトラストみどり財団と連携したイベント連携型の自然保護の啓発活動も推進されている。
流域・丘陵単位でのこうした活動の、もっとも大きな意義はどこにあるのだろうか。「いるか丘陵ネットワーク」(1995~、現在はNPO法 人流域自然研究会のネットワーク事業)の代表でもある岸氏は「100年、200年先の地べたとのつきあい方を正面から考えている」という。「今、私たちの文明の地球との付き合い方は、大地との付き合いの基本で間違っているのではないか。どこを開発するか、どこの自然を守るのか、せっかく大勢で議論していても、実は地球の刻んだランドスケープや水循環の基本地図が、そもそも共有されていないことが多い。ランドスケープが訴える可能性や制約を、もっともっと大切にしてゆくべきです」
人流域自然研究会のネットワーク事業)の代表でもある岸氏は「100年、200年先の地べたとのつきあい方を正面から考えている」という。「今、私たちの文明の地球との付き合い方は、大地との付き合いの基本で間違っているのではないか。どこを開発するか、どこの自然を守るのか、せっかく大勢で議論していても、実は地球の刻んだランドスケープや水循環の基本地図が、そもそも共有されていないことが多い。ランドスケープが訴える可能性や制約を、もっともっと大切にしてゆくべきです」
岸氏のいう「共通の地図」は、地理的な意味だけではないだろう。対話の土台という象徴的な意味でも、基盤となる価値を共有していなければ、実りのある議論はできないはずだ。
「日本は美しい列島です。その首都圏に、そうした認識を育むグリーンベルトがつくれれば、国際的にだって大きな影響力があるはず。その最適な候補地が、いるかの形の多摩・三浦丘陵群だと思っています。いるか丘陵ネットワークでの取り組みは、そんなビジョンを実現する力ともなってゆくと信じています。分断されていた多摩丘陵と三浦半島を1語で「多摩三浦丘陵群」と表現し始めて19年、鶴見川流域はバクの形と言い始めて17年、そして多摩・三浦丘陵群をいるか丘陵と呼び始めて10年。「いるか丘陵」や「バクの流域」を知る人はまだまだ少数派だが、こうした表現がごく自然に日常会話に上るくらいに、日ごろからランドスケープを意識する人が増え、私たちの地図が書き換えられてゆくことを願っています」
鶴見川流域や小網代をはじめとした「いるか丘陵」域の連携活動に呼応して、行政による都市部の自然環境の保護・保全や再生計画にも、徐々に流域・丘陵単位の視点が盛り込まれつつある。流域視野で安全、安らぎ、自然環境を重視した都市再生をめざす「鶴見川流域水マスタープラン」に続いて、たとえば、現在神奈川県が策定している「三浦半島公園圏構想」にも、横浜市金沢区・栄区、鎌倉市、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市の計4市1町2区にまたがる、流域・丘陵ベースの「水と緑のネットワーク」の構築がうたわれている。
自然環境本来の特質を生かした環境の保護・保全や再生を行おうと思えば、行政区限定ばかりではなく、流域や丘陵といった、ランドスケープに基づいた計画がぜひとも必要である。ランドスケープを基礎としたネットワークがさらに各地に広がり、多くの市民が長期的な視野に立った議論を重ねる必要がありそうだ。
小島和子@環境パートナーシップオフィス
